18世紀初頭 ナポレオン戦争と自由主義経済
19世紀前半の貿易は、政治的な大変動、新たな国際秩序の形成、そして技術革新という3つの大きな潮流によって大きく変貌しました。この時代は、保護主義から自由貿易への転換期であり、ナポレオン戦争、ウィーン体制、そして産業革命がその背景にありました。
ナポレオン戦争の影響
19世紀初頭のナポレオン戦争は、ヨーロッパ全土の貿易を根底から揺るがしました。特に重要なのが、1806年にナポレオンが発令した大陸封鎖令です。これは、イギリスと大陸ヨーロッパとの通商を禁止するもので、イギリス経済に打撃を与えることを目的としていました。
- イギリスへの影響: イギリスは大陸との貿易路を失いましたが、代わりに南米やアジアなどの新市場開拓を加速させ、世界的な貿易ネットワークを拡大する契機となりました。
- 大陸ヨーロッパへの影響: 大陸諸国はイギリスからの安価な工業製品が入手できなくなり、自国の工業化を促す結果となりました。これにより、一部の地域で独自の産業が発展し始めました。
ウィーン体制の影響
ナポレオン戦争後、1815年のウィーン会議によって国際秩序が再構築されました。このウィーン体制は、王政の復古と勢力均衡を目的とし、国際的な安定を目指しましたが、貿易面では国益を重視する保護貿易主義が主流となりました。
- 保護貿易主義の強化: 各国は戦争で疲弊した自国経済を立て直し、新興産業を育成するため、輸入品に関税を課す保護貿易政策を採用しました。これは、特に後発の工業国にとって、産業の土台を築く上で不可欠な政策でした。
- ドイツ関税同盟: この保護主義の代表例が、1834年にプロイセン主導で成立したドイツ関税同盟です。これは、加盟国間の関税を撤廃し、域外に対しては共通の関税を設けることで、ドイツ経済圏の統一と産業保護を図りました。
産業革命の影響
18世紀後半にイギリスで始まった産業革命は、19世紀前半には本格的に貿易のあり方を変え始めました。工業化による大量生産が可能になったことで、イギリスは圧倒的な工業力を手に入れました。
- 原料と市場の探求: 産業が発展するにつれて、工場を動かすための安価な原料(綿花など)と、大量に生産された製品を売りさばくための新たな市場が不可欠となりました。
- 自由貿易への転換: 産業の優位性を背景に、イギリスは自国に有利な貿易体制を求め始めました。これは、他国の関税をなくすことで、イギリス製品を世界中に輸出することを目的とする自由主義貿易へとつながっていきました。
自由主義貿易と保護貿易
19世紀前半の貿易は、この2つの経済思想の対立によって特徴づけられます。
- 自由主義貿易:
- 主張者: 産業革命で成功したイギリスが中心でした。
- 思想: 国家が貿易に介入せず、関税や規制を撤廃することで、各国が比較優位を活かした生産に専念すべきだという考えです。イギリスは自国の工業製品を安価に輸出することで、世界経済の覇権を握ろうとしました。
- 具体的な動き: 1846年の穀物法廃止や、1849年の航海法廃止など、貿易障壁を段階的に撤廃する動きがイギリスから始まりました。
- 保護貿易:
- 主張者: アメリカやドイツなどの大陸ヨーロッパの新興工業国が中心でした。
- 思想: 自由貿易は工業先進国(特にイギリス)に一方的に有利であり、自国の未熟な産業を保護するためには、高関税などの貿易制限が必要だという考えです。
- 具体的な動き: アメリカでは19世紀初頭から高関税政策が継続的に採用され、ドイツでもドイツ関税同盟が保護貿易の役割を果たしました。
この時代は、イギリスが主導する自由主義貿易の潮流が徐々に強まりつつも、後発国による保護貿易主義も根強く残る、過渡的な時期でした。
19世紀半ば 日本の開国
19世紀半ば、世界の貿易と関税は、アヘン戦争やアメリカ南北戦争といった歴史的な出来事を背景に大きく変化しました。この時代、ナポレオン3世のような指導者や、フランス二月革命、日本の開国、インド大反乱といった出来事が、国際的な経済関係に複雑に絡み合っていました。
自由貿易の台頭と国際関係
19世紀半ばは、自由貿易が世界的に広まった時期です。イギリスが主導し、国家間の関税障壁を取り払うことで貿易を活性化させようとする動きが強まりました。
- アヘン戦争: 1840年代、イギリスが清との貿易不均衡を是正するため、アヘン密輸をめぐって起こした戦争です。この結果、清は開国を強制され、不平等条約を結ばされました。これは、西洋列強が武力を用いて市場を開放させ、自由貿易を押し付ける典型的な例です。
- ナポレオン3世: フランス皇帝として、イギリスと英仏通商条約(コブデン=シュヴァリエ条約)を締結しました。この条約は、両国の関税を大幅に引き下げるもので、ヨーロッパにおける自由貿易の拡大に大きな影響を与えました。
- 日本の開国: 1853年、アメリカのペリー提督が来航し、日本は鎖国を解いて開国しました。その後、欧米列強との間で不平等な通商条約を結ばされ、関税自主権を失いました。これは、アヘン戦争後の清と同様に、西洋の圧力によって市場が開放された事例です。
内政と貿易・関税
一方で、各国の国内情勢も貿易政策に影響を与えました。
- フランス二月革命: 1848年にフランスで起こった革命です。これによって成立した第二共和政は、保護貿易を支持する勢力が影響力を持ちました。しかし、ナポレオン3世の第二帝政下で自由貿易に転換しました。
- インド大反乱: 1857年にインドで起こった、イギリス東インド会社に対する大規模な反乱です。この反乱は、イギリスの経済的搾取や文化的な干渉に対する不満が原因の一つでした。反乱後、イギリスはインドを直接統治下に置き、市場として完全に組み込むことで、貿易関係を一層強化しました。
- アメリカ南北戦争: 1861年から始まった内戦です。北部は工業が盛んで保護貿易を志向し、南部は綿花生産が中心で自由貿易を支持していました。この戦争は、経済政策の違いが大きな原因の一つでした。北部の勝利により、アメリカは保護貿易を基調とした工業化を進めることになりました。
また、南北戦争時は、アメリカからの綿花の輸出がストップ。綿花の産地である中央アジアの進出もこの時期に進んだ。
帝国主義
帝国主義(狭義)とは何か
帝国主義は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、主にヨーロッパの先進国(イギリス、フランス、ドイツなど)やアメリカ、そして日本が、工業生産に必要な資源の獲得や商品の販売先(市場)を求めて、アジアやアフリカの国々を植民地として支配していった動きや思想を指します。
これは、資本主義が独占段階へと発展した結果として起こったもので、単なる領土の拡大ではなく、経済的な利益追求がその核心にありました。この時期の帝国主義は、それ以前の植民地政策とは異なり、「新しい帝国主義(New Imperialism)」とも呼ばれます。
帝国主義が始まった理由
この時代の帝国主義が始まった理由は、第二次産業革命によって生まれた資本主義の構造変化に深く関わっています。
1. 資本主義の独占化
第二次産業革命により、石炭や鉄鋼を中心とする重工業が発展すると、巨大な設備投資が必要となりました。これにより、中小企業は競争に敗れ、資本力のある少数の企業が市場を独占するようになりました。これが独占資本です。
これらの独占資本は、さらなる利益を求めて、国内だけでは手に入らない資源と、国内市場だけでは消費しきれない生産物(商品)を売る場所を海外に求めるようになりました。
1870年代、過剰生産によりヨーロッパは不況に入ります。これにより、輸出のニーズが加速しました。
2. 経済的利益の追求
具体的には、以下の3つの経済的動機が帝国主義の推進力となりました。
- 原料供給地の確保: 工業生産に不可欠な資源(例:ゴム、石油、綿花)を安定的に安く手に入れる必要がありました。
- 市場(販売先)の確保: 大量生産された工業製品を販売する新たな市場が求められました。植民地は、本国の製品を強制的に買わされる「消費地」としての役割も果たしました。
- 資本輸出: 国内で余った資本を、植民地の鉄道建設や鉱山開発などに投資することで、より高い利益を得ようとしました。
3. 国家間の競争激化
独占資本が国家と結びつき、それぞれの国が経済的・軍事的な優位を競い合うようになりました。植民地獲得は、国力の象徴と見なされ、後発のドイツやアメリカ、日本も植民地獲得競争に参入し、世界の分割が進みました。この競争は、やがて第一次世界大戦の遠因の一つとなりました。
帝国主義は、資本主義の発達と、それに伴う国家間の経済的・軍事的競争が結びついて生まれた、近代特有の現象だと言えます。
1870年代〜80年代 アフリカ分割
この時期の国際貿易は、自由貿易から保護貿易への転換期であり、全体的な成長は鈍化しました。さらに、ドイツの外交政策(ビスマルク体制)とアフリカでの植民地獲得競争(アフリカ分割)が、国際経済と貿易に大きな影響を与えました。
1. 貿易の全体的な傾向と保護貿易主義への転換
- 成長の鈍化: 1873年に始まった大不況(長期不況)の影響で、1873年頃から1895年頃にかけて、世界の貿易成長率は停滞しました。
- 保護貿易主義の台頭: 大不況に直面した各国は、自国の産業を守るために輸入品に関税をかける保護関税政策を導入し始めました。
- ドイツとアメリカ: 後発の工業国であったドイツやアメリカは、イギリスに対抗するために保護主義を強めました。特にドイツではビスマルク政権のもとで関税が引き上げられました。
- 穀物貿易の激化: アメリカで安価に大量生産された穀物がヨーロッパに流入し、ヨーロッパの農業が打撃を受けました。これにより、各国は農業保護のために保護関税を導入する動きを強めました。
2. ビスマルク体制の影響
ビスマルクが主導したドイツ帝国は、1870年から1890年にかけて、ヨーロッパの国際秩序を安定させようとしました。この体制は直接的な貿易政策というよりも、国際的な緊張関係の緩和を通じて間接的に貿易環境に影響を与えました。
- 政治的安定の維持: ビスマルクはフランスを孤立させる外交政策を巧みに行い、ヨーロッパ列強間の大規模な戦争を回避しました。これにより、比較的安定した国際情勢のもとで各国は植民地獲得競争に注力することができました。
- 国内産業の保護: ビスマルク体制下のドイツは、鉄鋼や農業に関税をかけることで、国内産業の育成を推し進めました。この政策は、他国にも影響を与え、ヨーロッパ全体で保護貿易主義が広まる一因となりました。
3. アフリカ分割(Scramble for Africa)の影響
1880年代に入ると、ヨーロッパ列強によるアフリカ大陸の植民地化競争が本格化しました。
- ベルリン会議(1884-1885年): ビスマルクの主導で開催されたこの会議で、列強はアフリカをめぐる無秩序な競争を避けるため、支配地域の境界線などを取り決めました。これにより、植民地化が国際的に公認され、アフリカ分割がさらに加速しました。
- 植民地との貿易構造: アフリカの植民地は、ヨーロッパ諸国の工業生産に必要な原料供給地(ゴム、カカオ、ダイヤモンドなど)と、製品を売る市場として位置づけられました。この貿易構造は、植民地側の経済を単一作物に依存させる「モノカルチャー経済」へと変え、本国への従属を深めました。
- 貿易の地理的拡大: 植民地化により、それまで国際貿易のネットワークから外れていたアフリカの多くの地域が、本国を中心とする世界経済に組み込まれていきました。しかし、その貿易は列強の利益を第一とする不平等なものでした。
このように、1870年〜1890年の国際貿易は、経済的な大不況と、政治的な安定・競争の二つの側面が複雑に絡み合い、保護貿易主義と帝国主義的な貿易構造が形成されていく過渡期でした。
1890年代〜1900年代 ドイツの政策転換
ビスマルクが引退した1890年から第一次世界大戦が始まる1914年までの間、国際貿易と植民地政策は、帝国主義と保護貿易主義の激化によって大きく変化しました。この時期は、平和を維持しようとしたビスマルクの国際協調路線が崩壊し、各国が自国の利益を最優先するようになった時代です。
国際貿易の状況
この時代は、保護貿易主義が主流となりました。各国は自国の産業を保護するため、輸入品に高い関税をかけました。これは、ドイツがビスマルク引退後にヴィルヘルム2世のもとで工業力を急激に高め、イギリスと経済的に競争するようになったことが背景にあります。
- 関税障壁の構築: 主要な工業国は、国内市場を守るため、互いに高い関税をかけ合いました。
- ブロック経済の形成: 各国は、植民地との間で排他的な貿易圏(ブロック経済)を築き、植民地から原料を安く手に入れ、自国製品を高く売る仕組みを作り上げました。
植民地政策の状況
ビスマルク引退後の植民地政策は、新帝国主義へと移行しました。各国は、工業化によって増大した資本や生産物を投下する先、そして原料供給地や市場を確保するため、植民地獲得競争を激化させました。
- アフリカの分割: 19世紀末までに、アフリカ大陸のほぼ全域がヨーロッパ列強によって分割されました。特にイギリスとフランスが広大な植民地を獲得し、ドイツは出遅れました。
- ドイツの世界政策: ビスマルク引退後、ドイツのヴィルヘルム2世は「世界政策」を掲げ、海軍力を増強して植民地獲得競争に参入しました。これにより、既存の植民地大国であるイギリスとの対立が深まりました。ドイツの3B政策(ベルリン・ビザンティウム・バグダードを鉄道で結び、中東へ進出する政策)は、イギリスの3C政策(カイロ・ケープタウン・カルカッタを結ぶ政策)と衝突し、両国の緊張を高めました。
その影響
国際貿易と植民地政策のこれらの動きは、第一次世界大戦の遠因となりました。
- 国際的緊張の増大: 植民地をめぐる利権争いや、保護貿易主義による経済的対立が、各国間の不信感を高めました。特に、ドイツの積極的な植民地拡大は、イギリスやフランスといった伝統的な列強との間に深刻な対立を生み出しました。
- 軍拡競争の激化: 植民地と貿易ルートを守るため、各国は海軍力を中心とした軍備増強に走りました。特にドイツの海軍拡張は、イギリスとの間に軍拡競争を引き起こし、両国の関係を決定的に悪化させました。
これらの経済的・政治的対立が、やがて第一次世界大戦という全面的な軍事衝突につながっていったのです。
大日本帝国の台頭
当時の日本は、明治時代。89年に大日本帝国憲法(明治憲法)を制定し、立憲君主制へ移行した。
95年、日清戦争に勝利。清から台湾と澎湖諸島を割譲させ、巨額の賠償金を得て、その後の軍事力増強と産業発展の礎としました。また、朝鮮半島を清王朝から完全に独立させた。
05年、日露戦争に勝利。ポーツマス条約で遼東半島の租借権、南満州鉄道の利権などを獲得し、朝鮮半島における優越権を認めさせました。
10年、韓国を併合。この時期、日本は自国の工業製品の輸出先を求め、また原料供給地として朝鮮や満州への進出を強めていきました。
中国分割
清王朝は、列強の植民地化の危機に直面し、国内は混乱を極めました。
- 瓜分(うりわけ)の危機: 日清戦争での敗北後、列強は清に対してさらなる利権を要求し、租借地や鉄道敷設権などを次々に獲得しました。これは「瓜分の危機」と呼ばれ、清が事実上、列強によって分割される寸前の状態でした。
- 義和団事件: 1900年には、外国勢力への反発から義和団事件が勃発しました。列強は共同で軍隊を派遣してこれを鎮圧し、清への支配をさらに強めました。
- 辛亥革命と王朝の終焉: 欧米や日本の影響を受けた孫文らの革命運動が台頭し、1911年に辛亥革命が勃発。翌1912年に清は滅亡し、中華民国が成立しました。しかし、国内の混乱は続き、列強からの干渉も止みませんでした。
太平洋と米西戦争
18世紀後半に入ると、帝国主義は、ヨーロッパの裏側に当たる大西洋まで広がった。
最初に台頭したのがイギリスである。イギリスはオーストラリアを拠点に、太平洋の南西部(アジア側)の島々を獲得した。
フランスは、大西洋南東部(南米側)の島々に進出した。タヒチもその一つである。
日本(明治政府)は、小笠原初頭の領有権を各国に主張。太平洋北西部(アジア側)に勢力を広げた。
遅れてきた、ドイツは、赤道付近の西部(アジア側)の島々に進出。ビスマルク諸島がその一例である。
アメリカは、98年に米西戦争に勝利。スペインから東南アジアのフィリピンを獲得。同じ頃にハワイ王国を併合した。
10年代 第一次世界大戦
第一次世界大戦と国際貿易:グローバル化の衝突
第一次世界大戦は、単なる軍事衝突ではありませんでした。それは、当時の国際経済システム、特にグローバル化の進展と密接に関係していました。今回は、大戦が国際貿易に与えた影響、そしてその逆の関係について見ていきましょう。
大戦前の「第一次グローバル化」
19世紀末から第一次世界大戦が始まる1914年までの時代は、**「第一次グローバル化」**と呼ばれる時代でした。蒸気船や鉄道、電信の発達により、世界中の人、モノ、情報がかつてない速さで行き交いました。この時期には、国際貿易が飛躍的に拡大し、多くの国が経済的に結びついていきました。
特に、イギリスとドイツは経済的に深く相互依存していました。ドイツはイギリスにとって重要な貿易相手国であり、逆にイギリスもドイツに多くの製品を輸出していました。このような経済的な結びつきが、戦争を防ぐ抑止力になると考える人もいましたが、結果はそうではありませんでした。
帝国主義と貿易の競争
しかし、このグローバル化の裏側には、列強による帝国主義的な競争が隠れていました。工業製品の市場や原料を確保するため、各国は植民地の獲得をめぐって激しく対立しました。特に、新興国であるドイツは、多くの植民地を持つイギリスやフランスに比べて出遅れており、このことが経済的な不満と軍拡競争、特に英独の建艦競争を加速させる要因となりました。
国際貿易は、単なる経済活動ではなく、植民地獲得や軍備拡張といった政治・軍事的な対立と表裏一体の関係にあったのです。
大戦勃発と国際貿易の混乱
1914年に第一次世界大戦が勃発すると、国際貿易は一変します。
- 海上封鎖と通商破壊: イギリスはドイツに対する海上封鎖を実施し、ドイツは潜水艦による通商破壊でこれに対抗しました。これにより、世界の貿易網は分断され、物資の流通が大きく滞りました。
- 戦時統制経済: 各国は戦争遂行のために、経済活動を国家が統制する戦時統制経済へと移行しました。食料や軍需物資の配給、生産の管理が行われ、自由な貿易はほとんどなくなりました。
- 中立国の台頭: 欧米諸国が戦争に突入する中、参戦しなかった日本やアメリカは、戦争特需によって経済が大きく成長しました。特に日本は、欧米からの輸入が途絶えたことで国内の重化学工業が勃興し、輸出も急増しました。この「大戦景気」によって、日本は債務国から債権国へと転換し、「成金」と呼ばれる富豪も多く生まれました。
大戦後の世界経済
戦争終結後、世界の貿易はすぐに元の状態には戻りませんでした。戦争中に築かれたブロック経済や貿易の障壁は残り、国際的な協力体制は弱体化していました。さらに、1920年代には戦後恐慌、そして1929年には世界恐慌が発生し、各国は保護貿易やブロック経済をさらに強化しました。
この貿易の縮小とブロック経済の対立は、第二次世界大戦の遠因の一つになったと言われています。
まとめ
第一次世界大戦は、グローバル化が急速に進む中で、帝国主義的な競争が衝突した結果として発生しました。そして、戦争が始まると国際貿易は分断され、世界の経済システムは大きく混乱しました。この経験は、国際協調の重要性、そして経済的な結びつきが平和の万能薬ではないという教訓を私たちに残しています。
20年代 アメリカの黄金時代
第一次世界大戦と国際貿易:グローバル化の衝突
第一次世界大戦は、単なる軍事衝突ではありませんでした。それは、当時の国際経済システム、特にグローバル化の進展と密接に関係していました。今回は、大戦が国際貿易に与えた影響、そしてその逆の関係について見ていきましょう。
大戦前の「第一次グローバル化」
19世紀末から第一次世界大戦が始まる1914年までの時代は、**「第一次グローバル化」**と呼ばれる時代でした。蒸気船や鉄道、電信の発達により、世界中の人、モノ、情報がかつてない速さで行き交いました。この時期には、国際貿易が飛躍的に拡大し、多くの国が経済的に結びついていきました。
特に、イギリスとドイツは経済的に深く相互依存していました。ドイツはイギリスにとって重要な貿易相手国であり、逆にイギリスもドイツに多くの製品を輸出していました。このような経済的な結びつきが、戦争を防ぐ抑止力になると考える人もいましたが、結果はそうではありませんでした。
帝国主義と貿易の競争
しかし、このグローバル化の裏側には、列強による帝国主義的な競争が隠れていました。工業製品の市場や原料を確保するため、各国は植民地の獲得をめぐって激しく対立しました。特に、新興国であるドイツは、多くの植民地を持つイギリスやフランスに比べて出遅れており、このことが経済的な不満と軍拡競争、特に英独の建艦競争を加速させる要因となりました。
国際貿易は、単なる経済活動ではなく、植民地獲得や軍備拡張といった政治・軍事的な対立と表裏一体の関係にあったのです。
大戦勃発と国際貿易の混乱
1914年に第一次世界大戦が勃発すると、国際貿易は一変します。
- 海上封鎖と通商破壊: イギリスはドイツに対する海上封鎖を実施し、ドイツは潜水艦による通商破壊でこれに対抗しました。これにより、世界の貿易網は分断され、物資の流通が大きく滞りました。
- 戦時統制経済: 各国は戦争遂行のために、経済活動を国家が統制する戦時統制経済へと移行しました。食料や軍需物資の配給、生産の管理が行われ、自由な貿易はほとんどなくなりました。
- 中立国の台頭: 欧米諸国が戦争に突入する中、参戦しなかった日本やアメリカは、戦争特需によって経済が大きく成長しました。特に日本は、欧米からの輸入が途絶えたことで国内の重化学工業が勃興し、輸出も急増しました。この「大戦景気」によって、日本は債務国から債権国へと転換し、「成金」と呼ばれる富豪も多く生まれました。
大戦後の世界経済
戦争終結後、世界の貿易はすぐに元の状態には戻りませんでした。戦争中に築かれたブロック経済や貿易の障壁は残り、国際的な協力体制は弱体化していました。さらに、1920年代には戦後恐慌、そして1929年には世界恐慌が発生し、各国は保護貿易やブロック経済をさらに強化しました。
この貿易の縮小とブロック経済の対立は、第二次世界大戦の遠因の一つになったと言われています。
まとめ
第一次世界大戦は、グローバル化が急速に進む中で、帝国主義的な競争が衝突した結果として発生しました。そして、戦争が始まると国際貿易は分断され、世界の経済システムは大きく混乱しました。この経験は、国際協調の重要性、そして経済的な結びつきが平和の万能薬ではないという教訓を私たちに残しています。
30年代 ブロック経済
第一次世界大戦は、単なる軍事衝突ではありませんでした。それは、当時の国際経済システム、特にグローバル化の進展と密接に関係していました。今回は、大戦が国際貿易に与えた影響、そしてその逆の関係について見ていきましょう。
大戦前の「第一次グローバル化」
19世紀末から第一次世界大戦が始まる1914年までの時代は、**「第一次グローバル化」**と呼ばれる時代でした。蒸気船や鉄道、電信の発達により、世界中の人、モノ、情報がかつてない速さで行き交いました。この時期には、国際貿易が飛躍的に拡大し、多くの国が経済的に結びついていきました。
特に、イギリスとドイツは経済的に深く相互依存していました。ドイツはイギリスにとって重要な貿易相手国であり、逆にイギリスもドイツに多くの製品を輸出していました。このような経済的な結びつきが、戦争を防ぐ抑止力になると考える人もいましたが、結果はそうではありませんでした。
帝国主義と貿易の競争
しかし、このグローバル化の裏側には、列強による帝国主義的な競争が隠れていました。工業製品の市場や原料を確保するため、各国は植民地の獲得をめぐって激しく対立しました。特に、新興国であるドイツは、多くの植民地を持つイギリスやフランスに比べて出遅れており、このことが経済的な不満と軍拡競争、特に英独の建艦競争を加速させる要因となりました。
国際貿易は、単なる経済活動ではなく、植民地獲得や軍備拡張といった政治・軍事的な対立と表裏一体の関係にあったのです。
大戦勃発と国際貿易の混乱
1914年に第一次世界大戦が勃発すると、国際貿易は一変します。
- 海上封鎖と通商破壊: イギリスはドイツに対する海上封鎖を実施し、ドイツは潜水艦による通商破壊でこれに対抗しました。これにより、世界の貿易網は分断され、物資の流通が大きく滞りました。
- 戦時統制経済: 各国は戦争遂行のために、経済活動を国家が統制する戦時統制経済へと移行しました。食料や軍需物資の配給、生産の管理が行われ、自由な貿易はほとんどなくなりました。
- 中立国の台頭: 欧米諸国が戦争に突入する中、参戦しなかった日本やアメリカは、戦争特需によって経済が大きく成長しました。特に日本は、欧米からの輸入が途絶えたことで国内の重化学工業が勃興し、輸出も急増しました。この「大戦景気」によって、日本は債務国から債権国へと転換し、「成金」と呼ばれる富豪も多く生まれました。
大戦後の世界経済
戦争終結後、世界の貿易はすぐに元の状態には戻りませんでした。戦争中に築かれたブロック経済や貿易の障壁は残り、国際的な協力体制は弱体化していました。さらに、1920年代には戦後恐慌、そして1929年には世界恐慌が発生し、各国は保護貿易やブロック経済をさらに強化しました。
この貿易の縮小とブロック経済の対立は、第二次世界大戦の遠因の一つになったと言われています。
まとめ
第一次世界大戦は、グローバル化が急速に進む中で、帝国主義的な競争が衝突した結果として発生しました。そして、戦争が始まると国際貿易は分断され、世界の経済システムは大きく混乱しました。この経験は、国際協調の重要性、そして経済的な結びつきが平和の万能薬ではないという教訓を私たちに残しています。
40年代 第二次世界大戦
第二次世界大戦と国際貿易は深く関係しており、特に1929年の世界恐慌をきっかけとした保護貿易主義の広がりが、戦争の一因になったと考えられています。
戦前:保護主義とブロック経済の台頭
世界恐慌後、各国は自国の産業と雇用を守るため、高関税や輸入制限といった保護貿易政策を強めました。特にイギリスやフランスは、広大な植民地を巻き込んだ排他的なブロック経済圏を形成し、圏外の国々との貿易を制限しました。これに対し、植民地を持たないドイツや日本は、経済的な活路を求めて海外への市場拡大や領土拡張へと向かい、国際社会での緊張が高まりました。この経済ナショナリズムの台頭が、第二次世界大戦の遠因となったのです。
戦後:自由貿易体制の構築
第二次世界大戦の反省から、国際社会は保護貿易主義とブロック経済が戦争を引き起こしたという認識を共有しました。この反省に基づき、戦後は自由で多角的な貿易を推進するための国際体制が構築されました。
- GATT(関税と貿易に関する一般協定)の設立: 1948年に発効したGATTは、関税の引き下げや貿易障壁の撤廃を目的とし、自由貿易のルールを定めました。
- ブレトン・ウッズ体制: 1944年に設立が決定された**国際通貨基金(IMF)と国際復興開発銀行(IBRD、後の世界銀行)**は、国際的な金融安定と戦後復興を支援し、自由貿易体制を支えました。
これらの体制は、戦後の国際貿易の拡大と世界経済の安定に大きく貢献しました。第二次世界大戦は、保護主義がもたらす危険性を世界に示し、戦後の国際経済秩序を形作る決定的な転換点となったのです。🌍🤝📈

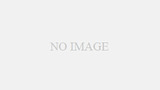
コメント