シルクロード
シルクロードは、古代から中世にかけてユーラシア大陸を東西に結んだ広大な交易路網であり、単なる物資の移動だけでなく、文化、宗教、技術、そして思想が交流する大動脈でした。その歴史は、東洋と西洋の主要な文明の興隆と衰退、そしてその間の多様な民族の活動と深く結びついています。
紀元前2世紀、中国の漢王朝が西方への探検を始め、大宛(フェルガナ)や大月氏(バクトリア)との接触を通じて、絹をはじめとする中国の産物が西方へ運ばれる道が開かれました。この交易路の西の終点の一つは遠くローマ帝国にまで及び、ローマの人々は中国の絹に熱狂しました。しかし、直接的な接触は少なく、間に多くの仲介者が存在しました。
中央アジアでは、1世紀から3世紀にかけてクシャーナ朝が栄え、シルクロードの中継貿易で大きな役割を果たしました。彼らは仏教の保護者でもあり、ガンダーラ美術に代表される仏教文化の東西伝播に貢献しました。この時代、シルクロードの安全を脅かす存在として、常に北方騎馬民族の存在がありました。彼らは遊牧生活を送りながら、時に交易路を支配し、時に略奪を行い、周辺の定住文明に大きな影響を与えました。
シルクロードの交易を実質的に担っていたのは、中央アジアのオアシス都市を拠点とするソグド人でした。彼らは優れた商業手腕と多言語能力を持ち、中国からビザンツ帝国に至る広範囲で活躍し、仏教やマニ教、ゾロアスター教などの宗教を東方へ伝えました。彼らのネットワークは、シルクロードの活気を支える上で不可欠な存在でした。
8世紀には、中央アジアの覇権をめぐり、イスラム勢力と唐王朝が衝突したタラス河畔の戦いが起こります。この戦いはイスラム勢力の勝利に終わり、中央アジアにおけるイスラム化が加速しただけでなく、製紙技術が西方に伝わるきっかけともなりました。
13世紀に入ると、モンゴル帝国がユーラシア大陸の大部分を支配し、広大な版図を統一しました。モンゴル帝国による「パクス・モンゴリカ(モンゴルの平和)」は、シルクロードの安全を飛躍的に高め、東西間の人や物の移動をかつてないほど活発にしました。マルコ・ポーロのような旅行者もこの時期に東方へと旅し、東西交流は最盛期を迎えました。しかし、モンゴル帝国の分裂と衰退、そして大航海時代の到来により、陸路のシルクロードはその重要性を徐々に失っていくことになります。
シルクロードは、単なる交易路ではなく、人類の歴史における壮大な文化交流の舞台であり続けました。
インド洋と海のシルクロード
サータヴァーハナ朝は、紀元前1世紀~紀元後3世紀にインド中部に栄え、海のシルクロードで重要な役割を果たしました。特にローマ帝国との季節風貿易が盛んで、胡椒や宝石を輸出し、ローマ金貨が流入。アリカメードゥなどの港が栄え、王朝の繁栄を支えました。
サータヴァーハナ朝衰退後、ローマ帝国の衰退に伴い西との交易は減少。代わりに東南アジアや中国との交易が重要視され、マラッカ海峡などが要衝に。セイロン島、扶南などが香辛料や陶磁器の交易で栄え、東方との結びつきが強まりました。
サータヴァーハナ朝衰退後、ローマ帝国の衰退で西との交易が縮小。7世紀頃からイスラーム商人がインド洋交易に本格的に台頭しました。彼らはペルシア湾岸を拠点に、インド西海岸、さらにはマラッカ海峡を越えて東南アジア、中国沿岸まで商圏を拡大しました。
インドでは、イスラーム勢力の侵入と王朝の成立により、ムスリム商人の活動が活発化しました。一方、東南アジアでは、軍事征服ではなく、ムスリム商人の経済活動を通じてイスラーム教が広まりました。特に13世紀以降、スマトラ島やマレー半島の港市でイスラーム化が進み、マラッカ王国がイスラームを受容したことで、教えは広く島嶼部に波及しました。交易がイスラーム化の大きな推進力となり、インド洋交易圏はイスラーム商人が主導する時代へと移行していきました。
デリースルタン朝(13世紀初頭~16世紀初頭)は、インドにおけるイスラーム政権として、その経済活動、特に貿易を活発化させました。この時代は都市経済が大きく発展し、貨幣が大量に発行されたことが特徴です。
貿易の中心を担ったのは、引き続きムスリム商人でした。彼らはインド沿岸の港を中継基地として活用し、西アジアと東南アジア、さらには中国を結ぶ「海の道」を活発に往来しました。胡椒などの香辛料、綿織物、宝石などがインドから輸出され、西アジアからは馬や貴金属、東南アジアや中国からは陶磁器や絹などが輸入されました。
大旅行家イブン・バットゥータがトゥグルク朝時代にインドを訪れ、その繁栄ぶりを記録していることからも、デリースルタン朝が国際貿易において重要な役割を担っていたことがうかがえます。
14世紀、東南アジアではジャワ島のマジャパヒト王国が海上交易で栄えました。また、タイでは14世紀にアユタヤ朝が成立し、チャオプラヤ川中流を拠点に交易を独占し発展しました。15世紀に入ると、南シナ海とインド洋を結ぶマラッカ海峡に位置するマラッカ王国が台頭。明の鄭和艦隊の来航を背景に、中継貿易港として飛躍的に発展し、香辛料や陶磁器などの交易が活発化しました。琉球王国も東南アジアとの交易を本格化させました。
日本と中国 朝貢貿易と密貿易
遣隋使以前、日本と中国王朝との交流は、西暦57年に倭の奴国が後漢に朝貢し、金印を授かったことに始まります。3世紀には、卑弥呼が治める邪馬台国が魏に使いを送り、親魏倭王の称号と金印、銅鏡などを授かりました。これは『魏志倭人伝』に詳しく記され、倭が中国の権威を背景に国内の統治を安定させようとしたことがうかがえます。その後、5世紀には「倭の五王」(讃、珍、済、興、武)が東晋・宋・南斉・梁といった南朝に繰り返し朝貢しました。これは朝鮮半島情勢と関連し、倭が冊封体制下で国際的地位を確立し、有利な外交を進めようとしたと考えられます。これらの交流は主に冊封体制下の朝貢・回賜という形で行われ、中国から先進的な文物や技術(鉄器生産、土木技術、織物など)がもたらされました。日本側はこれらを積極的に導入することで、社会や文化の発展を大きく進め、政治的な関係構築と共に、交易を通じて文化・経済的な交流が深まり、後の国家形成に大きな影響を与えたのです。
遣隋使・遣唐使の時代の交易は、主に朝貢・回賜の形式で行われました。日本からは銀、絹製品、水晶、火打ち金、瑪瑙、椿油などが貢ぎ物として贈られ、これに対し隋・唐からは錦などの高級絹織物、銀器、陶磁器、香料、医薬品、そして書籍(特に仏典)などが回賜品として与えられました。これらは単なる物品のやり取りだけでなく、中国の先進文化や技術の導入、仏教の伝来に不可欠な役割を果たしました。正倉院宝物には当時の交易品が多数残されています。
遣唐使廃止(894年)以降、日本と中国との公的な外交関係は途絶えましたが、民間レベルでの貿易は活発に継続されました。この時期の中国は宋王朝(北宋、後に南宋)であり、この貿易は日宋貿易と呼ばれます。
朝廷は一時、中国商船の来航制限(年紀制)や日本人の海外渡航禁止といった政策をとりましたが、中国の文物への需要は根強く、規制をかいくぐる形で交易が続けられました。10世紀後半に宋が中国を統一し、貿易を奨励するようになると、中国商船の来航はさらに増加します。
主要な拠点となったのは、九州の博多でした。博多には多くの宋人商人が居留地(唐坊)を形成し、国際都市として栄えました。
主な輸入品は、宋銭、香料、薬品、陶磁器、絹織物、書籍(特に仏典や漢籍)などです。特に宋銭は大量に流入し、当時の日本では貨幣経済が未発達だったため、国内の貨幣流通を大きく促進しました。
一方、日本からの輸出品は、金(奥州の砂金が有名)、銀、硫黄、水銀、真珠、そして刀剣や漆器などの工芸品でした。
12世紀に入ると、平清盛が日宋貿易の重要性に着目し、瀬戸内海の大輪田泊(現在の神戸港の一部)を整備するなど、積極的に貿易を推進しました。日宋貿易による莫大な利益は、平氏の経済基盤を支え、日本の文化にも大きな影響を与えました。
このように、遣唐使廃止後も日本と中国の交易は途絶えることなく、むしろ民間主導の「日宋貿易」として発展し、日本の社会・経済・文化に多大な影響を与え続けました。
鎌倉時代・南北朝時代の日本と中国の交易は、それぞれ中国の王朝の変化と日本の政治状況によって特徴が異なります。
鎌倉時代(中国:宋~元)
鎌倉時代は、前半が日宋貿易、後半が日元貿易の時代にあたります。
- 日宋貿易(鎌倉時代前半):遣唐使廃止後も続いていた民間貿易としての性格が強く、平清盛が推進した日宋貿易を引き継ぐ形で活発に行われました。鎌倉幕府もこの貿易による利益を重視し、九州の博多は国際貿易港として大いに栄えました。多くの宋人商人が博多に居住し、唐坊(外国人居留地)が形成されました。輸入品は、宋銭、香料、薬品、陶磁器(特に青磁・白磁)、絹織物、書籍(仏典・漢籍)など多岐にわたりました。特に大量に流入した宋銭は、日本の貨幣経済の発展を大きく促進しました。輸出品は、金(奥州の砂金が有名)、銀、硫黄(火薬の原料として需要が高まった)、水銀、真珠、そして日本刀や扇、螺鈿・蒔絵などの工芸品でした。
- 日元貿易(鎌倉時代後半):元寇(文永・弘安の役)によって日本と元の間には政治的な緊張が高まりましたが、経済的な交流は完全に途絶えることはありませんでした。元は日本を朝貢国にしようという意図もあって貿易を継続しようとしました。寺社造営の費用を捻出するために派遣された寺社造営料唐船などがその例で、半公的な性格を持つ貿易船も存在しました。有名な新安沈船(韓国沖で発見された元代の沈没船)は、まさにこの時代の日元貿易の実態を示す貴重な遺物です。主要な交易品は日宋貿易とほぼ同様で、日本からは金、日本刀、扇子、螺鈿、蒔絵、硫黄、銅などが輸出され、元からは銅銭、香料、薬品、書籍、茶、陶磁器などが輸入されました。
南北朝時代(中国:元~明)
南北朝時代は、中国では元の末期から明の初期にあたり、日本では南北朝の動乱期に重なります。
- 日元貿易の継続と衰退:鎌倉時代末期から南北朝時代にかけても日元貿易は続きましたが、元の衰退と日本の内乱によってその規模は縮小していきます。特に、倭寇(後期倭寇とは異なる、日本人による海賊行為)の活動が活発化し、中国沿岸や朝鮮半島を荒らしたため、中国側は日本に対して貿易の統制を求めるようになります。
- 日明貿易の始まり(南北朝末期~室町時代初期):中国で明が成立し(1368年)、日本で足利義満が南北朝を統一すると、倭寇対策と国家間の安定した関係構築を目指し、新しい貿易体制が模索されます。これが、有名な日明貿易(勘合貿易)です。南北朝時代の末期にあたる1401年(応永8年)、足利義満は僧の祖阿と博多商人の肥富を明へ派遣し、1404年(応永11年)には、明の永楽帝から「日本国王」の称号と勘合符を与えられ、勘合貿易が開始されました。これは、明の朝貢貿易体制の一部として行われ、日本が明の「臣下」として朝貢し、その見返りに回賜品を得るという形式でした。この貿易は室町幕府の重要な財源となり、倭寇の取り締まりにも寄与しました。
このように、鎌倉時代・南北朝時代の日本と中国の交易は、政治状況の変化に影響されつつも、中国からの先進的な物品や貨幣の流入、日本の産品の輸出を通じて、経済的・文化的な交流が継続・発展していきました。
中東・アフリカ イスラム商人
15世紀までの中東・アフリカの交易の歴史は、様々な民族や文化が交錯し、広範なネットワークを築き上げてきました。
初期の交易と古代文明
- フェニキア人: 紀元前12世紀頃から地中海交易を支配しました。彼らはレバノンを拠点に、木材(レバノンスギ)、染料(貝紫)、ガラス製品などを主要な輸出品とし、北アフリカ、特に現在のチュニジアにカルタゴを建設するなど、多くの植民地を築きました。これにより、地中海を介した中東と北アフリカの間の物資や文化の交流が活発化しました。
- アラム人: 紀元前12世紀頃からメソポタミアとシリアを中心に活動した内陸交易の担い手でした。彼らの言語であるアラム語は、古代オリエントの国際商業語として広く用いられ、情報伝達や契約の円滑化に貢献しました。ラクダを使った隊商貿易により、香辛料、織物、貴金属などがメソポタミアからシリア、さらにアラビア半島へと運ばれました。
- ギリシャ人: 紀元前8世紀頃から地中海世界に進出し、フェニキア人に代わって交易活動を活発化させました。彼らはエジプトやリビアなど北アフリカ沿岸にも植民地を築き、穀物、パピルス、香油などを輸入し、ワイン、オリーブオイル、陶器などを輸出しました。アレクサンドロス大王の東征以降は、ヘレニズム文化圏の拡大とともに、中東との交易も一層盛んになりました。
イスラム商人の台頭と交易ネットワークの拡大
- イスラム商人: 7世紀以降、イスラム帝国の拡大とともに、イスラム商人は中東、北アフリカ、そして東アフリカにおいて、圧倒的な交易ネットワークを構築しました。彼らは陸路ではシルクロード、海路ではインド洋貿易を支配し、中国、インド、東南アジア、ヨーロッパと広範囲にわたる交易に従事しました。
- 交易品: 香辛料、絹、陶磁器、金、銀、宝石、象牙、奴隷など多岐にわたりました。彼らは単なる物資の移動だけでなく、イスラム文化、技術、知識の伝播にも大きく貢献しました。
- 商業都市の発展: バグダード、カイロ、ダマスカス、アレクサンドリア、フェズといった都市が交易の中心地として繁栄しました。
東アフリカの交易
- 東アフリカ: 10世紀頃から、イスラム商人の来航により、独自の交易圏が発展しました。アラビア半島やインドからの商人は、モガディシュ、モンバサ、ザンジバル、キルワといった港市国家と交易を行い、象牙、金、鉄、木材、奴隷などを獲得しました。これらの港市は、内陸部のアフリカ諸国とインド洋を結ぶ重要な中継地となり、スワヒリ文化という独自の文化圏が形成されました。
アフリカ縦断貿易の展開
- アフリカ縦断貿易(サハラ縦断貿易): 15世紀までには、北アフリカと西アフリカを結ぶサハラ砂漠を越えた交易路が確立していました。この交易は、主に金、塩、奴隷が主要な交易品でした。北アフリカからは塩や織物、馬などが西アフリカへ運ばれ、西アフリカからは豊富な金が北アフリカ、さらに中東やヨーロッパへと送られました。この交易路は、マリ王国やソンガイ王国といった西アフリカの強力な国家の繁栄を支えました。
15世紀末にヨーロッパの大航海時代が始まると、中東・アフリカの交易は新たな局面を迎えることになりますが、それまでの長い歴史の中で築き上げられた交易ネットワークは、後の世界経済の基盤を形成する上で極めて重要な役割を果たしました。
ヨーロッパ ギリシャ商人から東方貿易まで
15世紀半ばまでのヨーロッパの商業史は、以下に挙げる語句を用いて概観することができます。
古代から中世初期にかけては、ギリシャ商人が地中海貿易において重要な役割を担っていました。彼らは植民地を拠点に、穀物、ワイン、オリーブオイルなどを取引し、広範な商業ネットワークを築きました。
その後に台頭したローマ帝国は、広大な版図と整備されたインフラ(道路、港湾)を背景に、地中海全域を支配する商業帝国を築きました。帝国内では統一された度量衡や通貨が用いられ、各地からの物資がローマに集積し、活発な商業活動が行われました。
ローマ帝国衰退後、ヨーロッパの商業は一時的に停滞しますが、中世盛期には再び活発化します。特に北ヨーロッパにおいては、北海とバルト海を結ぶ海運が発展しました。この地域で大きな影響力を持ったのが、北ドイツの商業都市が結成したハンザ同盟です。彼らは主に毛織物、魚、木材、琥珀などを扱い、北海沿岸からロシア内陸部に至る広大な地域で商業的な覇権を確立しました。ハンザ同盟は独自の法律や軍事力を持ち、加盟都市間の貿易を保護・促進しました。
一方、地中海世界では、十字軍以降に東方貿易が隆盛を極めました。ヴェネツィアやジェノヴァといったイタリアの都市国家がその中心となり、香辛料、絹、宝石などの東方からの貴重な品々をヨーロッパ各地に供給しました。東方貿易は莫大な富をイタリア商人ににもたらし、ルネサンスの経済的基盤を築きました。
15世紀半ば、特にオスマン帝国の台頭による東方貿易路の変化や、大航海時代の幕開けは、これまでのヨーロッパの商業構造に大きな変革をもたらすことになりますが、それまでの商業活動は、ギリシャ商人、ローマ帝国、北海、ハンザ同盟、そして東方貿易といった要素が複雑に絡み合いながら発展していったと言えます。

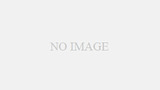
コメント