15c〜16c 大航海時代
大航海時代は、15世紀半ばから17世紀半ばにかけてヨーロッパの国々が主導した、地球規模の海洋探検と新航路開拓の時代です。主な動機は、オスマン帝国の台頭による東方貿易路の閉鎖、香辛料や金銀などの富を直接獲得したいという経済的欲求、そしてキリスト教の布教熱でした。
ポルトガルはエンリケ航海王子の支援のもと、アフリカ西岸を探検し、バルトロメウ・ディアスが喜望峰を発見。ヴァスコ・ダ・ガマがインド航路を開拓しました。スペインはクリストファー・コロンブスによるアメリカ大陸到達を皮切りに、マゼランの世界一周航海を支援するなど、新大陸の探検と征服を進めました。
この時代は、世界の地理的知識を飛躍的に拡大させ、ヨーロッパ中心の世界経済システムを確立しました。しかし、同時に先住民の文化や社会の破壊、奴隷貿易の拡大といった負の側面ももたらしました。大航海時代は、その後の世界史の展開に決定的な影響を与えた重要な転換点となりました。
17c オランダの台頭
17世紀のオランダは、世界経済の覇権を握る海洋国家として台頭しました。その背景には、以下のような要因があります。
アジアでの覇権
オランダがアジアで覇権を握った主な理由は、強力な東インド会社(VOC)の存在です。VOCは国家に準ずる権限を持ち、軍事力と商業力を兼ね備えていました。彼らは香辛料貿易の利潤を独占するため、ポルトガルやスペインからアジアの交易拠点を次々と奪い、特にインドネシアのモルッカ諸島を支配下に置きました。1623年のアンボイナ事件では、イギリス東インド会社の商館員を処刑し、これによりイギリスを香辛料貿易から締め出し、独占体制を強化しました。また、進んだ造船技術と航海術も、長距離貿易を有利に進める要因となりました。
衰退の理由
しかし、17世紀後半になると、オランダの覇権は陰りを見せ始めます。最大の要因は、イギリスとの度重なる衝突、特に英蘭戦争です。航海条例をめぐる経済的対立は、3次にわたる戦争に発展し、オランダは莫大な戦費と人的損害を被りました。また、フランスのルイ14世による大陸進出も、オランダの国力を疲弊させました。さらに、金融・貿易の中心がロンドンに移り始めたこと、そして貿易国家として生産基盤が脆弱であったことも、長期的な衰退に繋がりました。限られた国土と人口は、常に大国との競争において不利に働き、徐々にその影響力を失っていったのです。
大西洋三角貿易
大西洋三角貿易は、ヨーロッパ、アフリカ、アメリカ大陸を結ぶ交易ネットワークであり、その開始、内容、終焉には様々な要因が絡み合っています。特に「アシエント」は、この貿易システムにおいて重要な役割を果たしました。
始まったきっかけ
大西洋三角貿易が始まった主なきっかけは、15世紀末から16世紀にかけてのヨーロッパ諸国による新大陸発見と植民地化でした。新大陸には豊富な天然資源(金、銀、砂糖、タバコなど)が存在し、これらの資源をヨーロッパへ持ち帰ることが経済的な目的となりました。しかし、新大陸の先住民の人口はヨーロッパから持ち込まれた疫病や過酷な労働によって激減し、労働力不足が深刻化します。
そこで目を付けられたのが、アフリカからの奴隷でした。アフリカでは古くから奴隷制度が存在しており、ヨーロッパの商人はアフリカの王国や部族間の対立を利用して奴隷を調達しました。初期にはポルトガルが奴役貿易を主導しましたが、やがてスペイン、イギリス、フランス、オランダなどが参入し、組織的な奴隷貿易が確立されていきました。
アシエント(Asiento)
「アシエント」とは、スペイン王室が特定の個人や会社に与えた、アフリカからスペイン領アメリカへの奴隷供給契約の独占権のことです。スペインは広大な植民地を抱えていましたが、自国で奴隷を調達する能力が十分でなかったため、このアシエント制度を通じて他国の商人に奴隷供給を委託しました。
アシエントは、奴隷貿易を合法化・制度化し、その規模を拡大させる上で極めて重要な役割を果たしました。アシエントを獲得した企業や個人は莫大な利益を上げ、その富はヨーロッパ経済に大きな影響を与えました。特に18世紀にはイギリスがアシエントの主要な担い手となり、カリブ海の砂糖プランテーションにおける奴隷労働力の供給を独占することで、イギリス経済の発展を大きく加速させました。
内容
大西洋三角貿易は、大きく以下の三つのルートで構成されていました。
- ヨーロッパからアフリカへ: ヨーロッパの商船は、銃、火薬、繊維製品、金属製品、酒類などの工業製品や雑貨を積んでアフリカ西海岸へ向かいました。これらの商品は、アフリカの奴隷商人や部族長との間で奴隷と交換されました。
- アフリカからアメリカ大陸へ(中間航路): 奴隷を積んだ船は、大西洋を横断してアメリカ大陸の植民地(主にカリブ海の島々やブラジル、アメリカ南部)へ向かいました。この航路は「中間航路 (Middle Passage)」と呼ばれ、奴隷たちは船内で非人道的な環境に置かれ、多くの者が病気や飢餓、虐待によって命を落としました。
- アメリカ大陸からヨーロッパへ: アメリカ大陸に到着した奴隷は、プランテーションや鉱山で強制労働に従事させられ、生産された砂糖、タバコ、綿花、コーヒー、金、銀などの一次産品がヨーロッパへ輸出されました。これらの産品はヨーロッパ市場で高値で取引され、巨額の利益を生み出しました。
このサイクルは、ヨーロッパの産業革命を支える資本蓄積に貢献し、ヨーロッパ諸国の経済発展を大きく促進しました。同時に、アフリカからは数千万人に及ぶ人々が奴隷として連れ去られ、アフリカ社会と経済に壊滅的な影響を与えました。
終わったきっかけ
大西洋三角貿易が終焉を迎えたきっかけは、主に以下の要因が挙げられます。
- 奴隷制度廃止運動の高まり: 18世紀後半から19世紀にかけて、ヨーロッパやアメリカにおいて奴隷制度に対する倫理的批判が高まり、廃止運動が活発化しました。啓蒙思想の影響やキリスト教人道主義の普及が背景にあり、クエーカー教徒などが中心となって奴隷貿易と奴隷制度の不当性を訴えました。
- 経済的合理性の変化: 奴隷労働は、一見すると安価な労働力に見えましたが、実際には奴隷の維持費、監督者の人件費、逃亡奴隷のコスト、反乱のリスクなど、様々なコストがかかりました。また、産業革命の進展により、工場での自由労働者による生産の方が効率的であるという認識が広まり、奴隷労働の経済的合理性が疑問視されるようになりました。
- 政治的圧力と国際条約: イギリスは1807年に奴隷貿易を禁止し、その後も他の国々に奴隷貿易の廃止を促す国際的な圧力をかけました。イギリス海軍はアフリカ沿岸で奴隷船を拿捕するなど、積極的な取り締まりを行いました。これにより、奴隷貿易は徐々に非合法化され、困難になっていきました。
- 奴隷の抵抗と反乱: アメリカ大陸の各地で、奴隷による抵抗や反乱が頻発しました。特にハイチ革命(1791年-1804年)は、奴隷による大規模な反乱が成功し、独立を達成した画期的な出来事であり、奴隷制度の維持が困難であることを示しました。
これらの要因が複合的に作用し、19世紀半ばまでにはほとんどの国で奴隷貿易が廃止され、奴隷制度自体も順次廃止されていきました。大西洋三角貿易は、人類史上最も非人道的な交易システムの一つとして、その歴史に深い傷跡を残しました。
英仏植民地百年戦争
第二次英仏百年戦争の影響
1. インドへの影響
第二次英仏百年戦争の期間中、インドはイギリスとフランスの植民地争奪戦の主要な舞台の一つとなりました。特に、1740年代から1760年代にかけてのカーナティック戦争(第一次、第二次、第三次)は、両国がインドの現地勢力と同盟を結び、互いの勢力圏を拡大しようとしたものです。
- イギリスの優位確立: 第三次カーナティック戦争(七年戦争の一部)において、イギリスはプラッシーの戦い(1757年)とヴァンディヴァッシュの戦い(1760年)でフランスに決定的な勝利を収めました。これにより、フランスはインドにおける主要な政治的・軍事的影響力を失い、貿易拠点のみを維持する形となりました。
- イギリス東インド会社の台頭: イギリス東インド会社は、フランスの排除後、ムガル帝国の衰退に乗じてインド支配を急速に拡大し、最終的にはインド亜大陸の大部分を支配するイギリス領インド帝国の基礎を築きました。
2. アメリカ大陸への影響
アメリカ大陸もまた、英仏間の激しい植民地争奪の場となりました。
- フレンチ・インディアン戦争(七年戦争のアメリカ大陸戦線): 1754年から1763年にかけて戦われたこの戦争は、北米におけるフランスの支配を終わらせる決定的なものでした。イギリスはフランスからカナダ、ミシシッピ川以東のルイジアナを獲得し、北米における最大の植民地勢力となりました。
- アメリカ独立革命への影響: フレンチ・インディアン戦争で多大な戦費を費やしたイギリスは、その費用を賄うために北米植民地への課税を強化しました。これが植民地住民の不満を高め、最終的にアメリカ独立革命(1775-1783年)へと繋がりました。フランスはイギリスへの報復としてアメリカ独立戦争を支援し、アメリカの独立を助けましたが、その莫大な戦費がフランス革命の一因ともなりました。
3. 国際交易の変化
これらの戦争は、国際交易の構造に大きな変化をもたらしました。
- 重商主義の加速と競争激化: 各国は自国の富を最大化するため、植民地からの資源獲得と製品輸出を重視する重商主義政策を強化しました。これにより、植民地と本国を結ぶ交易路の支配を巡る競争が激化しました。
- イギリスの海洋覇権確立: 一連の戦争を通じて、イギリスはフランス、スペイン、オランダといったライバル国を打ち破り、世界の海洋における圧倒的な覇権を確立しました。これにより、イギリスは広大な植民地ネットワークと安全な海上交易路を確保し、後の産業革命の基盤を築きました。
- 大西洋経済圏の拡大: 奴隷貿易を含む大西洋を横断する交易(三角貿易)が拡大し、ヨーロッパ、アフリカ、アメリカ大陸を結ぶ経済圏が強化されました。
4. 戦費の調達方法と国家財政への影響
これらの長期にわたる大規模な戦争は、参戦国の国家財政に甚大な影響を与えました。
- 戦費調達方法:
- 課税の強化: 各国は、戦争遂行のために国民からの税金(消費税、地租、関税など)を大幅に引き上げました。
- 国債の発行: 国債を発行して国内外から資金を借り入れることが主要な資金調達手段となりました。特にイギリスは、中央銀行であるイングランド銀行を基盤とした効率的な国債発行システムを確立し、多額の戦費を調達する能力に優れていました。
- 借款: 他国や銀行からの借款も行われました。
- 植民地からの収益: 植民地からの資源や税金も戦費に充てられました。
- 国家財政への影響:
- 国家債務の増大: 戦争が長期化するにつれて、イギリスとフランスの両国で国家債務が劇的に増加しました。特にフランスは、効率的な徴税システムと国債市場が未発達であったため、財政状況が深刻化し、これがフランス革命の遠因の一つとなりました。
- 財政改革の必要性: 増大する債務は、各国に財政改革の必要性を突きつけました。イギリスは効率的な財政管理と税制改革を進めましたが、フランスでは改革の失敗が革命へと繋がりました。
- 金融システムの発展: 戦費調達の必要性から、国債市場や銀行システムといった近代的な金融システムが発展しました。
5. 日本・清王朝への影響
第二次英仏百年戦争は、直接的には日本や清王朝(中国)に大きな影響を与えることはありませんでした。この時期、両国はそれぞれ独自の外交政策をとっており、ヨーロッパの紛争からは距離を置いていました。
- 日本: 江戸時代中期から後期にあたり、鎖国政策を維持していました。ヨーロッパの動乱は、一部の蘭学者などを通じて情報が伝わることはありましたが、国家としての直接的な関与や影響はほとんどありませんでした。しかし、この時期にイギリスやロシアなどの船が日本近海に出没するようになり、後の開国への圧力の遠因となる動きは見られました。
- 清王朝: 乾隆帝の時代から嘉慶帝の時代にあたり、最盛期を迎えていましたが、ヨーロッパ列強の動きに対しては「中華思想」に基づき、自らを世界の中心と見なしていました。イギリスは清との貿易(特に茶の輸入)を拡大しようとしていましたが、清は貿易を広州に限定し、厳しい規制を設けていました。この時期の英仏の戦争は、清の国内政治や社会に直接的な影響を与えることはありませんでしたが、ヨーロッパ列強の経済力と軍事力の増大は、後のアヘン戦争(1840-1842年)に代表される清への圧力へと繋がっていきます。
要するに、これらの戦争はヨーロッパ列強の勢力均衡を大きく変え、特にイギリスの海洋覇権と植民地帝国の確立を決定づけました。その影響は、インドやアメリカ大陸といった植民地地域には直接的かつ甚大なものでしたが、当時の日本や清王朝には直接的な影響は限定的でした。しかし、長期的に見れば、ヨーロッパ列強の台頭と世界経済の再編は、やがてこれらの東アジアの国々にも大きな変化をもたらすことになります。
大英帝国とアヘン戦争
18世紀末、フランス革命が始まり、19世紀に入るとナポレオン戦争が展開される。これにより、オランダやフランスなどの大陸諸国は混乱する。この混乱に乗じて対応したのが、イギリスこと大英帝国である。
18世紀前半の大英帝国の植民地政策は、主に重商主義の原則に基づいていました。これは、本国の富を増やすために植民地を経済的に利用するという考え方です。植民地は原材料を供給し、本国の工業製品の市場となることで、本国の貿易黒字を最大化することが目指されました。この政策は、国家が貿易を厳しく管理し、金銀の蓄積を重視することで国富を増やすというものでした。
この時期、イギリスは特にアジア貿易において、イギリス東インド会社を主要な担い手としていました。イギリス東インド会社は、インドにおける貿易拠点を拡大し、現地の支配力を徐々に強めていました。彼らは香辛料、綿織物、茶などの貴重な商品をヨーロッパへ運び、莫大な利益を上げていました。この会社の活動は、単なる貿易にとどまらず、軍事力を行使して現地の政治に介入するようになり、後のインド支配の基礎を築いていきました。
また、大英帝国は植民地獲得と貿易覇権を巡って、ヨーロッパの他の主要国、特に海洋貿易で先行していたオランダと激しく競合していました。17世紀には英蘭戦争を通じてオランダの海上覇権を徐々に奪い、18世紀に入ると、北米、カリブ海、インドなど世界各地で植民地を巡る争いが続きました。この競争は、イギリスが世界的な海洋国家としての地位を確立する上で不可欠な要素でした。
重商主義から自由貿易への転換の萌芽
18世紀後半になると、スコットランドの経済学者アダム・スミスが、重商主義の考え方に疑問を投げかけました。彼は1776年に著書『国富論(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)』を発表し、国家が貿易に介入するのではなく、個人の自由な経済活動に任せる「自由貿易」こそが、真の国富をもたらすと主張しました。スミスは、市場における「見えざる手」が、個人の利益追求を通じて社会全体の利益を最大化すると説き、植民地も本国の経済的利益のためだけに存在するという重商主義的な考え方を批判しました。
アダム・スミスの思想は、当初は緩やかにしか受け入れられませんでしたが、産業革命の進展とともに、自由貿易の考え方はイギリスの経済政策に徐々に浸透していきました。これにより、植民地は単なる資源供給地や市場としてだけでなく、自由な経済活動の場として捉えられるようになり、後の植民地政策の転換点となりました。
ご提示いただいた「フェートン号事件」、「ナポレオン戦争」、「アヘン戦争」は、18世紀後半から19世紀にかけての出来事であり、18世紀前半の植民地政策の直接的な説明には含まれませんが、その後の大英帝国の植民地拡大と政策の変化を示す重要な転換点となります。
- ナポレオン戦争(1803-1815年頃)は、19世紀初頭にヨーロッパを巻き込んだ大規模な戦争であり、この戦争を通じてイギリスはフランスやその同盟国から多くの植民地を獲得し、世界的な覇権を不動のものとしました。特にオランダがフランスの支配下に入ったことで、オランダの植民地(ケープ植民地など)がイギリスの手に渡る結果となりました。
- フェートン号事件(1808年)は、ナポレオン戦争中にイギリス海軍のフリゲート艦フェートン号が日本の長崎港に侵入した事件です。これは、当時の日本の鎖国政策下において、イギリスがアジアにおける活動範囲を広げていたことを示す一例ですが、18世紀前半の植民地政策そのものとは直接関係ありません。
- アヘン戦争(1839-1842年)は、19世紀半ばにイギリスが清国(中国)との間で起こした戦争であり、これによりイギリスは中国市場へのアクセスを強制し、香港を獲得しました。これは、大英帝国の植民地政策が、単なる資源獲得から市場の確保、さらには非西洋諸国への影響力拡大へとシフトしていったことを象徴する出来事です。
このように、18世紀前半のイギリスは重商主義と貿易競争に重点を置いていましたが、19世紀に入ると、ナポレオン戦争やアヘン戦争のような出来事を通じて、その植民地支配はさらに広範かつ強固なものへと変貌していきました。そして、アダム・スミスに代表される自由貿易の思想は、その後の大英帝国の植民地政策の方向性を大きく変えることになります。

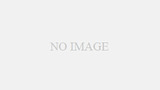
コメント