皆さん、こんにちは!いよいよ7月14日、フランス革命記念日がやってきますね。この記念すべき日に、歴史の裏側に隠された、とんでもないつながりをご紹介しようと思います。今回は、遠く離れた日本とフランスで起きた大事件、「天明の大飢饉」「浅間山噴火」そして「フランス革命」が、実は一本の線で結ばれていたという驚きの物語を、べらぼうに掘り下げていきます!いま、大河ドラマべらぼうでも、舞台になっている天明の米騒動も今回のテーマになっています。
1. 日本を襲った悲劇:天明の大飢饉と浅間山噴火
1783年、日本の歴史に深く刻まれる大災害が起こりました。それは、浅間山の大噴火です。この噴火は、大量の火山灰や軽石を噴出し、周辺地域に壊滅的な被害をもたらしました。
噴火の影響はそれだけに留まりませんでした。噴火によって巻き上げられた火山灰やエアロゾルは成層圏まで達し、太陽光を遮断。その結果、日本列島全体で異常な冷夏が続き、稲作は大凶作に見舞われました。これが、1782年から1788年にかけて日本を襲った天明の大飢饉の決定的な引き金の一つとなったのです。
飢饉は全国に広がり、餓死者や病死者が続出し、社会は大混乱に陥りました。農村は荒廃し、都市部でも米価が高騰し、打ちこわしが頻発するなど、当時の社会システムを大きく揺るがす事態となりました。
2. 海を越えた影響:パン価格高騰とフランス革命
さて、この浅間山の噴火が、遠く離れたヨーロッパ、特にフランスにまで影響を及ぼしていたとしたら、皆さんは驚かれるでしょうか?
浅間山から噴出したエアロゾルは、偏西風に乗って地球規模で広がり、北半球の気候に大きな影響を与えたと考えられています。ヨーロッパでは、浅間山噴火の数年後、異常な寒波や長雨が続き、農作物が壊滅的な被害を受けました。特に、フランスでは主食である小麦の収穫量が激減し、それに伴いパンの価格が記録的な高騰を見せたのです。
当時のフランスでは、貧しい人々にとってパンは生命線でした。パンの価格高騰は、彼らの生活を直撃し、飢えと困窮は日ごとに深刻化していきました。政府の無策や貴族の贅沢に対する民衆の不満は頂点に達し、この経済的苦境が、1789年に勃発するフランス革命の直接的な引き金の一つとなったと言われています。
「パンがなければお菓子を食べればいいのに」というマリー・アントワネットの言葉(真偽は定かではありませんが)が象徴するように、当時の支配層と民衆の間にあった意識の乖離は、パンの価格高騰によってさらに深まり、革命への道を加速させました。
3. 気候変動が歴史を動かす
このように、1783年の浅間山噴火は、遠く離れた日本の天明の大飢饉を引き起こしただけでなく、地球規模の気候変動を通じて、フランスのパン価格高騰、ひいてはフランス革命という世界史を大きく変える出来事にも間接的に影響を与えていた可能性があるのです。
自然災害が人類の歴史に与える影響の大きさを改めて感じさせられる話ではないでしょうか。現代においても気候変動が大きな課題となる中で、過去の歴史から学ぶべきことは多いのかもしれません。
皆さんも、この壮大な歴史のつながりについて、ぜひ考えてみてくださいね。

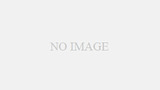
コメント